
Nstockは、SmartHRグループを離れ、独立したスタートアップになりました。
先日の「SmartHRの取締役退任ブログ」でも少しだけふれていましたが、その後の手続きが全て完了し、ようやく正式に発表できる状態になりました。
対応にあたったSmartHR & Nstockの皆さん、ありがとうございました。特に、獅子奮迅の活躍をみせたNstock保坂さんにはBIG感謝です。
AI時代、独立ブログで何を書こう?
これまでブログで色々書いて来ましたが、今回は「何を書こう?」と珍しく悩みました。
起業家ブログはあくまで広報活動の一つで「宣伝ではあるんだが、役に立つ情報があるので読んでもらえる」みたいなものだと思っています。
しかし、だいたいの正解はAIが教えてくれる時代になりました。これまでだったら、「どうやって独立したのか?そのスキームは?」みたいなテーマで書いてたかなと思います。それもニーズがあるのかなとは思いつつ、今回は次の3点をメインに書いていこうと思います。
- なぜ最初から独立しなかったの?
- 私なりの「起業が成功する秘訣」
- 社員が3.2億円も株を買ったストーリー
これからは、How to みたいな起業家ブログのニーズは減っていって、判断の裏にある「意思や感情」「ストーリー」を書くほうがウケるのかなと思っています。違ったら誰か教えてください。
2の「起業が成功する秘訣」に関しては How to っぽいですが、これまで日本のスタートアップ業界ではアンチパターンとされていた要素が多いので、これも(本日時点では)AIが教えてくれない情報かなと思って書きます。
まずは前提となる独立の概要
本日のプレスリリースの通り、SmartHR社が保有するNstock株式のセカンダリー取引と、第三者割当増資を組み合わせ、多数のステークホルダーによる株式取得を実施しました。
最終的な取得金額(概算)は下記です。
- 代表取締役 宮田昇始:6億円
- Nstock社員等 約40名:3.2億円(!!!)
- Nstock株式会社:2億円
- ベンチャーキャピタル 5社(既存株主):6.8億円
- WiL
- Coral Capital
- 千葉道場ファンド
- East Ventures
- ALL STAR SAAS FUND
結果、SmartHR社のNstock株式保有比率は、約65%から約14.5%まで下がり、連結子会社および持分法適用会社のいずれにも該当しなくなります。
ちなみに、どんな流れでNstockが独立することになったのかの詳細は、明日5/14(水)にオウンドメディア「Stock Journal」で「SmartHRのCFO視点で振り返る、グループ会社 Nstock の創業から独立まで。」という記事が公開されるので、そちらをチェックしてみてください。こちらの記事にも、独立に至るストーリーや判断の背景がたくさんあります。
最初から独立してれば、約7.5億円いらなかったのでは…?
さて本題です。
宮田は、昨年の30億円の資金調達時と、今回の独立にあわせた取引で、合計で約7.5億円もの資金をNstock株の取得に費やしています。
Nstockは、宮田がSmartHRのCEOを退任した2022年1月に創業した会社です。創業のタイミングから独立したスタートアップとして始めていれば、払う必要がなかった7.5億円とも言えます。
当然、7.5億円の買い物は人生のなかで圧倒的に一番大きな買い物ですし、今回もスキームを整理していくなかで「ぼくも…6億円分…買い増します……!」と発言した際には Google Meet 越しにめっちゃ震えました。
「なぜ最初から独立しなかったのか??」
3年前の自分に、自分が一番聞きたい。と思いつつ、不思議と後悔はありません。当時の気持ちなどを紐解いてみました。
なお、合計7.5億円もの資金は、宮田が保有するSmartHR株式の一部を2024年のセカンダリー取引で売却した売却益から捻出しています。(セカンダリーすごい)
なぜ最初から独立しなかったの?
当時は、正直にいうと悩んでいました。
身銭を切る形で創業し、シードで外部から資金調達をすることも出来たと思います。もっと言うと、その時点で自分のSmartHR株式をセカンダリーで売却したら、外部からの資金調達もいらない形で経営できたかもしれません。
しかし、最終的には「いまは独立せず、SmartHRのグループ会社として創業しよう」と決めました。
理由は大きく次の3点です。
理由1. 先輩起業家からのアドバイス
当時、シリアルアントレプレナーの先輩に相談したことがあります。彼から「SmartHRグループ内でやるのが一番いいのでは?少なくとも外部資本は入れてもらったほうがいい」というアドバイスをもらい、これが自分的にはしっくり来ました。
アドバイスを要約すると、
- いま独立すると、規律がなくなって、自分を省みれなくなってしまうのではないか?真っ当な指摘に対しても「自分が身銭きってるんだから好きにやらせろ」と感じてしまう
- それで失敗しても、Facebookとかで「応援してます」「次回も期待してます」みたいなコメントがあふれる(応援してもらえるのはうれしいことなんだけど、それでは反省できないよね)
みたいな感じでした。
当時のぼくは、自分が創業したSmartHRがユニコーン企業になったばかりという自信と、大きくなっていく会社にしばられることへの窮屈な気持ちを持っていて、もともとの性格もどちらかというと弱い人間ということもあり「わかる〜〜!実際そうなりそう〜〜!」と強く共感しました。
SmartHRグループ内なのか、外部VCさんから資金調達をするのか、いずれにせよステークホルダーと利害を一致させながら、ある程度は規律をもって起業するほうが、当時の自分には合っているな、2回目も成功確率を高められそうだと感じました。
理由2. さみしさ、友人の多くはSmartHRメンバー
端的に言うと「SmartHRを離れる心の準備ができていなかった」です。
CEOを交代することと、自分が創業した会社を完全に離れることは、似ているようで違うことです。前者は「関係性の変化をともなう役割の交代」であり、後者は「関係性自体が極端に薄くなること」だと思います。
当時から3年が経ったいまだからこそ前向きな気持ちで離れられますが、当時はまだその心の準備ができていませんでした。
そもそもぼくは、事業を大きくしようと思って起業したわけではなく、良いメンバーとワクワクしながら楽しく働きたいと思って、SmartHR社(当時の社名はKUFU社)を起業しました。その優先度は、おそらくまわりの起業家と比較して非常に高いです。
また、ぼくは休日に遊びにでかける相手も、平日に飲みに行く相手も、その多くが(娘と)社内メンバーです。Nstock創業時は、よく遊ぶ友人たちがSmartHRメンバーだったので、そこから離れるということはさみしいという思いが強かったです。
今では、Nstockにも良いメンバーがたくさん集まり、ワクワクしながら楽しく働けています。また、ようやくSmartHRの人達と離れてもさみしくない、いつでも会えるという安心感もうまれて、独立する心の準備ができたんだと思います。
理由3. 立つ鳥跡を濁さず
下記は、明日公開予定の「Stock Journal」の森さんのインタビュー記事からの引用です。
宮田:ちなみに、「資本関係のない別会社をつくってそこにSmartHRから出資する」という形ではなく、「SmartHRの100%子会社としてのスタート」は、どんな背景でしたっけ?
森:2022年1月に宮田さんがSmartHRの代表取締役CEOを退任する際には、株主含めたステークホルダーから「創業から会社を引っ張ってきた宮田さんが経営から離れて大丈夫なのか」という心配の声がありました。
SmartHRの代表は変わるものの、宮田さんは引き続き取締役として経営に関与しつつ、100%子会社でシナジーの見込める新規事業を行うのは、個人的にもとても良い折衷案だと思い、グループ会社での事業開始という形をとりました。
宮田:す、すみません(苦笑)。
そうなんです。
まだ当時はステークホルダーたちにも不安があり、その状態で無理やり独立した会社をつくっても「CEOが交代するだけでも不安なのに、全く資本関係のない別会社をつくるなんて……!」と、まとまる話もまとまらなかった気がします。
理由1 & 理由2と通じる話でもありますが、なによりSmartHR社とそのステークホルダーに迷惑はかけたくなかったというのが大きかったです。
ちなみに、CEO交代から3年たってSmartHRは引き続き業績好調なので、今回はステークホルダーの皆さんから特に不安の声は上がりませんでした。(それはそれでさみしいけどね!)
まとめ: なぜ最初から独立しなかったの?
まとめると、ぼく視点では下記の3点が重要だったかなと思います。
- 適度な規律をもつことで、2回目起業でも成功確率を上げたい
- 当時はSmartHRを離れる心の準備ができていなかった(現在はできている)
- 突然のCEO交代 + 別会社起業で、会社やステークホルダーに迷惑をかけたくなかった
なので、100%子会社としてSmartHRグループでのスタートは気持ちがよかったですし、いまも後悔はないです。
あと、SmartHRグループでNstock事業をスタートしたからこそのメリットもたくさん享受できました。コーポレート業務、マーケ業務、公共政策、イベント登壇してもらう、面接に出てもらう等、さまざまなサポートをしてもらえました。これらの手厚いサポートのおかげで、事業に集中できて、いまのNstockの状態まで持ってこれたなと思います。
たぶん、タイムマシンで3年前に戻ったとしても100%子会社からスタートすると思います。
私なりの「起業が成功する秘訣」
さて、2つの目の話題です。
結論から言うと、私なりの起業を成功させる秘訣は「会社とメンバーの利害を、非常に強いレベルで一致させること」です。
- 会社が大成功したら、自分の人生も大成功する。(だから絶対成功させる!)
- この会社がなくなったら困る。(だから絶対つぶさせない!)
この状態をつくることができれば、大きく成功確率を上げることができると本気で思っています。
しかし、言うは易しで、なかなか難しいです。
非常に強いレベルで、利害を一致させる方法とは?
根性論だけでは絶対無理。ミッションへの共感だけで完全に満たす、満たし続けることも、難しいと思っています。
そこで利害を一致させるツールとして活用されているのが「ストック・オプション(SO)」です。SOを活用することで、ミッションの実現や働きがいだけでなく、「会社の成功が、自分の経済的な成功にもつながっている」という状態をつくることができます。
そんなSOよりも、さらに強力なのがセカンダリーや第三者割当増資を通じて「会社の株式を購入してもらうこと」だと思っています。
SOも十分にすごいツールです。しかし、株式の購入はよりパワフルに作用します。これはSOか株式かという形式の話よりも、「身銭を切るという行為がともなった」「自分の意思に関係なく与えられたものではなく、自分の意思でリスクをとって購入したもの」という要素が重要なのだと思います。
実は、SmartHRの初期にも当時のキーパーソンたちに、SmartHR株式を何度かセカンダリーで買ってもらっています。
特に覚えているのは、2017年に実施したセカンダリー取引で、私と共同創業者2名から、当時のキーパーソン数名に対して合計で5%ほどの売却を行いました。当時、競合サービスが一気に増えたこともあり、キーパーソンを社外流出させないため、より利害を一致させてもらうために購入機会を設けました。
もちろん本人に買う意思があることが大前提で、強制はできません。もし仮にとんでもないブラック企業が、社員に強制で株を買わせたとしても、たぶんその株式に利害を一致させる効果はありません。会社の将来性に賭ける意思がなければ買ってもらえませんし、買ってもらったとて意味がありません。
2017年のSmartHRは、まだ確実に成功するか誰にもわからないタイミングではありましたが、親族に借金をしてまで追加購入したメンバーもいます。そのときの購入者の多くがその後にCxOやVPになり、SmartHRの初期の急成長に大きな貢献をしてくれました。
当時の購入者へのインタビューもありますので、よければチェックしてみてください。 journal.nstock.com
社員に株を持ってもらうことはアンチパターン?
私がSmartHR事業をはじめた2015年ごろの話ではありますが、当時は社員に株を買ってもらう行為は「悪手」「避けたほうがいいこと」として、教わることが多かったです。
おそらく、創業者間での揉め事があった際に、辞めた共同創業者からの株の買い戻しに苦労するケースが多く発生したことから、このような教えが広まっているのかなと思います。創業期は会社のカルチャーも定まってないので採用もミスりやすく、ピボットすることも珍しくないので、共同創業者が辞めるケースも多いでしょう。確かにその買い戻しは大変ですし、この教えの背景も理解できます。
実際に、2017年当時のぼくもメンバーに株を買ってもらうこと自体にビビッていて、購入機会を各部門の責任者だけに絞っていました。
ある社員と一緒に夕飯を食べた帰り道に「SmartHRの株を買いたい」と言われて、めちゃくちゃうれしかったんですが、当時のぼくは勇気をもって売ってあげれなかったことに今でも後悔してます。(一生ご飯をおごるのでゆるしてくれ〜!)
さて、確かにリスクがあることは事実ですが、一回起業してユニコーン企業をつくったいま感じることは、これも数あるリスク/リターンの一つでしかなく、リターンが欲しいならリスクを取るべきです。
会社とメンバーの利害を非常に強いレベルで一致させ、事業に強くコミットした組織をつくれるリターンに比べると、問題が起こったときのリスクは大したことはないんじゃないでしょうか?退職時に買い戻すのか戻さないのか、そのときの条件や算定方法をどうするかなどを事前に決めておけば、問題が起こった際の労力は最小限に抑えることもできると思います。
なんならこのブログも誰かに dis られるんじゃないかとビビりながら書いていますが、このブログで読んだことを実践したスタートアップが大成功し「あのブログのおかげです」と言ってもらえるリターンを信じて書いています。
繰り返しになりますが、メンバーに株を強制で買わせちゃダメですし、買ってもらってもおそらく意味がないのでやめておきましょう。逆に株の購入を持ちかけられた社員の皆さんは、その会社の将来性に賭けられないと思ったら、株式購入の打診があっても勇気を出して断りましょう。
社員が3.2億円も株を買ったストーリー
さて、今回SmartHRから独立するに際して、最終的に18億円ものNstock株の取得が行われました。
プレスリリースを見て驚かれた方も多いと思いますが、なんとNstock社員 約40名が、合計で3.2億円もの株式を購入してくれています……!誰かが1億円買っているとかではなく、中央値も数百万円後半です。みんなすごい。
この金額規模で社員が株を取得するなんて、日本のスタートアップ業界ではかなりエポックメイキングな出来事だと思うので、このストーリーを紹介させてください。
Nstockの資金調達を機に、独立の話が再スタート
話は、昨年実施したNstockの30億円の資金調達までさかのぼります。
VCさんからの資金調達の話をすすめている時点で、Nstockの独立は既定路線でした。下記は、明日公開予定の「Stock Journal」の記事からの引用です。
森:個人的にはNstockでの資金調達の議論をしている時点で、将来的なSmartHRグループからの独立は既定路線だと考えていました。SmartHRに投資している株主と、Nstockに投資している株主の利害を両立させることはやはり難しく、Nstockが連結子会社の状態でお互いの株主価値を最大化することは難しいと容易に判断できました。
ということで話が進み始めますが、独立するためにはNstock株を買い取る必要があります。
独立の議論は、実は1〜2年前にもしたことがありました。しかし、当時のNstockは外部調達を実施していない = Nstockの株に値段がついていない状態だったので、価格の合意形成が難しそうと判断し、ペンディングになりました。
それが、Nstockの資金調達を機に株価が付いたことで、価格交渉の合意形成の難易度が大きく下がり、スムーズに独立の話が進み始めます。
しかし、連結子会社および持分法適用会社のいずれにも該当しなくなるめには、全部で18億円というかなり大きな金額を用意する必要があるとわかりました。
誰が18億円も用意するのか?
今回、取引されたNstock株式は「普通株式」です。前回の資金調達では投資家に有利な条件がついている「優先株式」をつかって資金調達しているので、今回の普通株式のバリュエーション(評価額)は、優先株式の金額と比較して割安です。
既存株主のVCさんからするとお得なようにも見えるかもしれません。しかし、そもそもかなりプレミアムを乗せたバリュエーションで投資してもらっているので、割安だとしても高いです。また、各ファンドには1社に投資できる上限が設定されているのが一般的なので、割安だったとしても必ずしも今回も株を買ってもらえるとは限りません。
経営株主(宮田)の持ち分を高めるチャンス
また、宮田からすると保有比率を高めるチャンスでもあります。社員と同様、経営者が会社と利害を一致させるためにも株の保有は重要です。今回のように、スタートアップがスピンアウトするとき、スピンアウトした側の経営株主の持ち分が少なくなってしまうという問題がありますが、これを一気に解消できるまたとない機会です。
しかし、1つ問題がありました。宮田は引き続きSmartHRの創業者で大株主の1人です。SmartHRの重要な関係者という扱いになり、宮田の保有比率が高すぎると、持分法から外れなくなるという問題がありました。その上限金額が約6億円でした。ただ、いま実際に使える最大の金額でもあったので、現実的にこれ以上買増することは難しかったです。
これで昨年の1.5億円とあわせて、合計で7.5億円もの金額をNstock株の取得に費やしたことになります。さすがに今回の6億円は震えるほどの覚悟(実際に震えた)が必要だったので、ギアが1段階上がった気がします。絶対Nstockを成功させるぞ。
「Nstock社員のみんなに声かけてみようか?」
宮田が6億円分買ったとしても、残り約12億円です。ここで「せっかくなので、既存株主の皆さんに打診する前に、Nstock社員のみんなに声かけてみようか?」というアイデアが出ます。
資金調達時に声掛けする人数は49名以下にする必要があるため、既存株主 + そのタイミングで所属している社員 + 外部協力者など若干名が声掛けできる最大の人数でした。
ちょっと記憶が曖昧なのですが Weekly Allhands かなにかで、今回の独立の概要と、希望者には株を購入する機会を用意すること、意向を知りたいのでまずはアンケートに回答して欲しい(この時点では確定ではない)旨を社員の皆さんにお伝えしました。
予想外のアンケート結果を見て「ちょっと落ち着いてもらおう」
「10〜15人くらい買ってくれて、5,000万円くらい集まったらいいな〜」という期待値でしたが、アンケートで集まった回答はまさかの1.5億円ほどと、予想外の金額でした。ぼくと事務局をやってくれていた保坂さんは当然びっくりして、「これはちょっとやりすぎだよね」という話になり、一旦みんなに落ち着いてもらうために、次のようなメッセージを伝えることにしました。
- 株をたくさん買ってくれようとしているのはめちゃくちゃうれしい
- でも、無理に買って欲しいとはまったく思っていません
- もし生活を切り詰めて買おうとしているのであれば、オススメしません
- 将来の経済的な成功も大切ですが、いまの生活や、いま思い出をつくることも大事です
- 無理して買おうとしていないか、冷静になって考えたり、ご家族と相談してみてください
このメッセージは、アンケート翌週の Weekly Allhands で、宮田が口頭でお伝えした気がします。
これでちょっとは落ち着くかなと思ったのですが、2回目のアンケートでまさか約2倍の3.2億円に増えるという現象が起きました。なぜ?
なんで3.2億円も買ってくれたのか?
何名かのコメントを紹介したいと思います
- 「どうせ数年間は働くので、大成功したときのリターンを大きくしたい」
- 「前職でキャピタルゲインを得た成功体験があったので、積極的に買いたいと思った」
- 「家族に相談したら、『全力で買えるだけ買おう!』となりました」
- 「もしユニコーンになれなくても、いまの評価額くらいでM&A売却は絶対できると思った」
- 「一回、株主を経験してみたかったから」
- 「以前所属した会社で、株を買わずに大きく後悔した経験があるので、今回はチャンスを逃したくなかった」
- 「家族でお金の話をしたり、自分のお金と向き合ったり、将来の自分と向き合ったり、その営み自体にめちゃめちゃ価値がある」
最後めちゃいい話……。それぞれに理由があるんだなと思いました。
その後と、今後
さて、残り7.8億円ですが、2億円はNstock社による自己株式取得、5.8億円は既存株主VCの皆さんに買ってもらえることになりました。繰り返しになりますが、実態と比べて決して安い評価額ではないので、本当にありがたいです。
ちなみに、既存VCの皆さんとのMTGで、社員からの3.2億円の購入希望があることを伝えたら、皆さん思わず笑ってしまうほどビックリされていました(笑)。社員が株を買うことと、その金額規模を聞いて、追加投資を決めたVCさんもいらっしゃいました。
ただ、この金額規模感はどのスタートアップでもできることではなく、Nstock固有の事情もあると思います。
- 前職等でキャピタルゲインを得て資金に余裕がある人が多い
- 株やSOで成功体験がある人や、逆に失敗体験がある人が多い
- 事業ドメイン的にSOや未上場株のリテラシーが高い
しかし、少人数であっても、少額であっても意味があると思うので、スタートアップ経営者の皆さんはぜひ自社でも検討されてみてください。
Nstockでも、今後入社してくる人達も対象に、セカンダリーでNstock株式を購入できる機会も用意していきたいと思っています。
締めの前に、告知です。(もう少し続きます)
今回の独立に関連した内容をお話するイベントを2つ開催予定です。
■ 5月28日(水)【オフレコ】SmartHRのグループCFOは、Nstockの独立をどうジャッジしたのか?
まず1つ目。こちらは SmartHR CFO 森さんに "CFO目線で" Nstockの独立を語ってもらいます。オフレコの話も出ると思うので、オフラインでのリアル開催イベントです。
↓ お申し込みはこちら
https://nstock.com/news/event_20250528
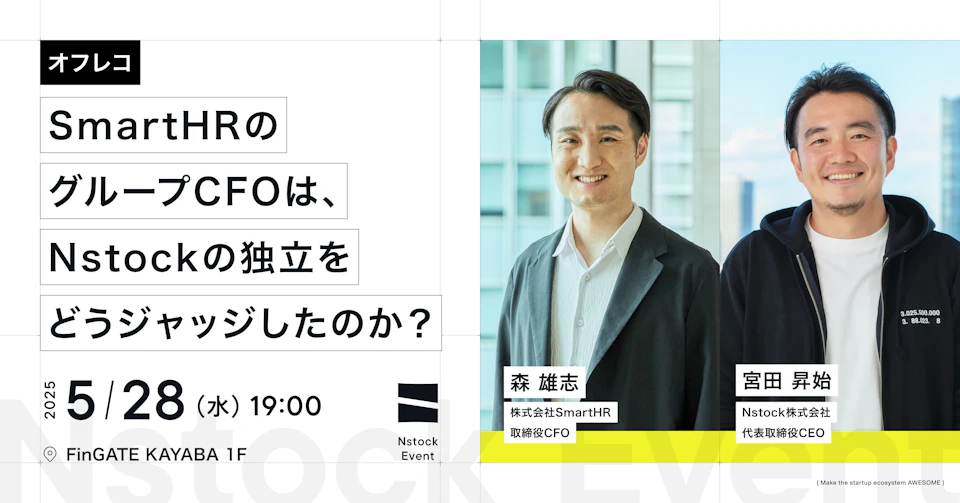
■ 6月3日(火)【仮説】社員に経営目線を持ってもらうには株買ってもらうのが一番だよね?
そして2つ目。こちらは「社員による3.2億円の株式購入」をメインテーマにしたイベントです。こちらはZoom配信のオンライン開催です。
イベントは2部構成で、前半は会社側の立場から本件を実施した理由などを解説し、後半は実際に株式を購入した社員が登壇してリアルな声をお届けします。
↓ お申し込みはこちら
https://nstock.com/news/event_20250603
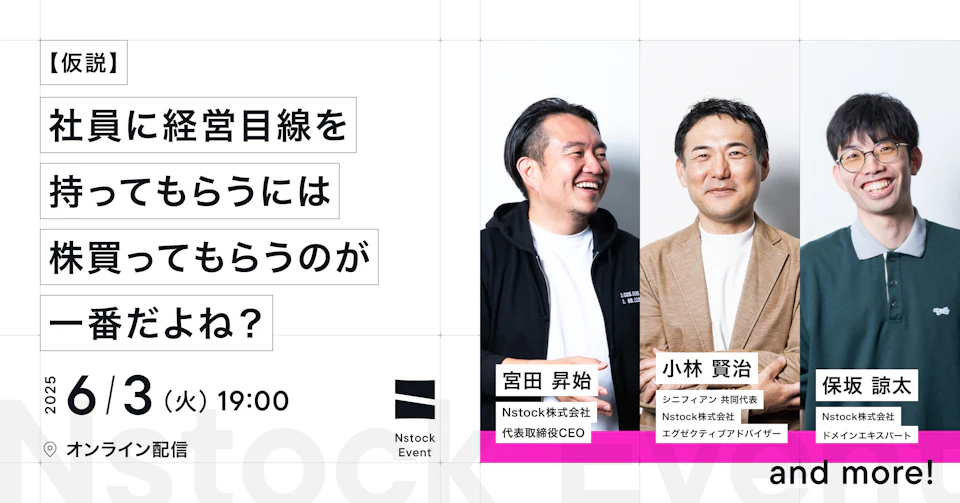
それと、独立にあたってコーポレート業務の内製化を急いでいます。労務、法務の求人が出ていますので、よければぜひ。 エンジニアさんやデザイナーさんも、引き続き募集中です。
採用サイトはこちら↓ recruit.nstock.co.jp
最後に
さて、最後に自分のプレスリリースのコメントを引用したいと思います。
今回の独立は、Nstockの第二創業とも言える節目です。特に、社員の皆さんが自らのお金を投じてNstockの株主となってくださったことに心から感謝しています。私自身も追加で6億円を投じており、この事業にかける覚悟と情熱はこれまで以上に強くなっています。今後もより一層全員でNstock事業に向き合い、スタートアップ業界をより良くしていきたいと考えています。SmartHRにはこれまでの多大な支援に深く感謝し、今後は良きパートナーとして協働してまいります。
会社の将来性に賭けて株を買ってくださったNstock社員の皆さん、そして今回も追加で資金を投じてくださった既存株主の皆さん、本当にありがとうございます。
ぼく自身も、Nstock社との利害がより強くなり、会社を成功させざるを得ない状況になりました。これまで以上にがんばっていきたいと思います。
そしてSmartHRグループの皆さん、Nstockの創業から3年間ありがとうございました。これからも株主として、Nstock導入企業として引き続きよろしくお願いします。
日本語ラップ好きの皆さんへ
一部の方から「ブログの最後の日本語ラップコーナーを復活してほしい」という声をいただくので、しばらく復活しようと思います。
Benjazzy - UNTITLED
今回はBenjazzyの「UNTITLED」を紹介します。ちゃんと聴いたのこの曲が初めてだったんですが、フローが特徴的だと思いきや、リリックもめちゃいいんですね。Chaki Zuluのトラックもかっこいいです。
以下、引用
偽わったまま演じ生きる
より好きに生きて出すNG
他人の人生の脇役で終るなよ
やり直してるいつか思うあの日の今を
エキストラ 名無しで未だUNTITLED
アドリブで変える台本
一本撮りでかからないカット
本音のサントラが鳴るエンドロール
金じゃ買えない財産を築きHOODの顔
役張って 錆ねぇ金字塔打ち立て
ここで終わりゃ1番綺麗っての分かってる
から心電図みたいに脈打つ
波形自ら止めては死んだ様に生きてた
けどそん時親父の癌と
母親の網膜剥離を聞き支払う
目に焼き付けたステージに上がったギャラ
ンティでステージを下げれた親父の癌
親不孝のドラ息子から今じゃ
うちの子はドームアーティストと喜ぶ親
じゃあもし俺がRapやってなかったらって
あの日夢見てた自分に心臓を叩かれる
ご両親が病気になって、その治療費を Benjazzy 氏が支払った話なんでしょうが、「網膜剥離 × 目に焼き付けた」「ドームのステージ × 癌のステージ」で掛かってるとことか、「ドラ息子 × ドームアーティスト」で韻踏んでるとことかめちゃ好きです。
BAD HOP で売れて、燃え尽きてたけど再燃した的なリリックも自分の境遇と重なって刺さりました。
偽わったまま演じ生きるより 好きに生きて出すNG、でやっていきたい
おわり